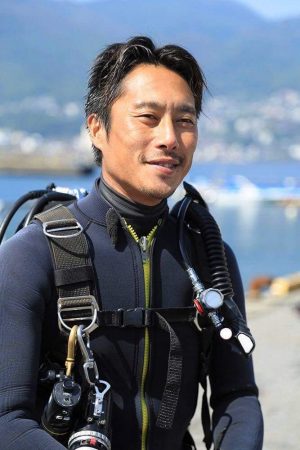春濁りはなぜ起こる?意外と知られていないその原因に迫る!
朝晩冷え込む日はあるものの、暦の上では4月5日ごろは清明(せいめい)にあたり、万物に清新の気がみなぎる時節。ようやく春到来といったところで、そろそろ海に繰り出す冬眠ダイバーたちも多いのでは。ところがこの時期は、海の透明度がさがる「春濁り」現象が起きるタイミングでもある。ところによっては透明度1m、なんてことも。そこで本記事では、ダイバーにとって厄介な春濁りはなぜ起こり、いつ終わるのかなど、実はあまり知られていない(!?)意外なメリットについてもご紹介していこうと思う。
【目次】
春濁りはなぜ起こる?

Photo by Dive Family Yellow 川坂秀和さん
春濁りとは、植物プランクトンの大量発生によって海の透明度がさがる現象のこと。主に春先に起こるため、ダイバーの間で生み出された俗語のようだ。同現象のメカニズムは以下のとおり。
1、秋から冬にかけての水温差が比較的少ない時期は、水の層の境界線(サーモクライン)ができにくく、海の上層と下層の水は循環され、下層に沈殿していた栄養豊富な海水は上層に。
↓
2、そこへ、春の温かな日差しが降り注ぐなどで水温が上昇すると、栄養豊富な海水の力(※)で植物プランクトンが一気に増殖。
基本的に、この1~2のメカニズムで春濁り現象は起こるのだが、冬場育った海藻類が枯れ、水温の上昇と共に溶け出すことも一因という。
※下層に沈殿していたものだけでなく、この時期には中国大陸から飛んでくる黄砂によって砂漠のミネラルが海の栄養分となり、植物性プランクトンの繁殖を下支えしているともいわれている。
春濁りはいつ始まり、いつ終わる?

Photo by Dive Family Yellow 川坂秀和さん
透明度がさがってしまえば、フィッシュウォッチングを主な目的とするダイバーにとっては一大事。春濁りの時期は正確に把握しておきたいもの。しかしながら、自然現象なので、いつからいつまでという明確な線引きはなく、おおむね3月下旬から4月中にかけて発生するといわれている。発生してから終わるまでは大体数週〜1か月ほどかかるなどといわれているが、年によっては発生しないこともあるのだとか。確実なのは、お世話になる現地ダイビングショップに海の状況を確認することだろう。
春濁りでもダイビングを楽しむ方法ってあるの?

Photo by Dive Family Yellow 川坂秀和さん
ここからは意外なメリットについて、春濁りの影響を受ける代表的なエリアの一つである、東伊豆・伊東をホームグラウンドとして活動するダイビングショップ・ダイブファミリーイエロー(Dive Family Yellow)の川坂秀和さんにお伺いする。
メリット1:どこの海でもダイビングを楽しめるようになる

Photo by Dive Family Yellow 川坂秀和さん
春濁り現象が強く発生すれば、海の透明度が低くなるのは事実。しかし、それを逆手にとって考えてみると、普段から透明度が低い海を見慣れていれば、5m見えただけでも、「あ、今日は透明度が高いな」と感じられるのではないだろうか。「透明度が高いことは、あくまで、ダイビングを楽しむための一要素です。春濁りの海も知っておくことで、楽しめる幅が増えると思います」。と川坂さん。ちなみにこの時期にダイビングを始められた方は、ダイビング自体を続けられる方が多いそう。
メリット2:ガイドを独り占めしてスキルアップに勤しむチャンス

Photo by Dive Family Yellow ゲストさま
春濁りの時期はまだまだ水温が低いため、潜りに来るダイバーも少ない。これはガイドを独り占めする絶好のチャンス。上記写真にあるように、水中撮影をマンツーマンでサポートしてもらったり、中性浮力をはじめとする様々なダイビングスキルを向上させてみたりと自分の技術向上に役立ててみては。
メリット3:春濁りならではの水中写真が撮れる&撮影技術も向上する
フォト派ダイバーに朗報!この時期ならではの魅力的な水中写真が撮れるという。例えば、‟黒抜き”のワイド撮影もその一つだ。

NikonD810 16-35mm ストロボ撮影(キンギョハナダイの群れ)Photo by Dive Family Yellow 川坂秀和さん
川坂さん
この時期に個人的によく撮るワイドの黒抜き写真。ワイドだと、どうしても自然の明るさを拾ってしまい、背景がうっすら明るくなりやすいため、‟黒抜き‟は通常マクロ撮影で多用されますが、この時期はすでに背景が暗いことが多いので、ワイドでもこのような背景を暗くした写真が撮りやすいなと。春濁りだからこそ撮影できる写真かなと思っています。
透明度が低い中で撮影するからこそ、ライティングの工夫など、この環境下でしか学べないようなことも学べるというわけか。
また、この時期は、海の色が独特のグリーンになるという特徴をもっている。撮影していると、グリーンの背景が綺麗に感じることさえあるという。春濁りらしい海の色を活かした写真(※)がこちら。

Panasonic GX7MK3 panasonic14-24mm+INON UFL-M150ZM80 ストロボ撮影(ハコフグとソフトコーラル)Photo by Dive Family Yellow 川坂秀和さん
(※)写真は、2020年8月に撮影されたもので、一般的な春濁りの状態に近いもの。2020年は、新型コロナウイルスの緊急事態宣言下だったため、写真データなし。
川坂さん
透明度3〜5mのコンディションの中撮影された一枚で、被写体のハコフグまで15cmというところまで近寄っています。太陽の位置などによっても変わりますが、視界が悪いのは魚も一緒のようで、ストロボだけ付けて、そうっと呼吸をして近づけば、魚に寄りやすいんです。ストロボの光の回し方や被写体との距離感、レンズの使い心地などを勉強したり試したりするには最高の状態なのではないでしょうか。自分の撮影技法の幅や水中写真の経験値を広げるきっかけにもなりますし。背景の独特なグリーンも、四季を持つ日本の海ならではの特徴が出ていてお気に入りです。

上記写真と同じ装備で撮影されたカサゴとソフトコーラル。カサゴまでの距離は5cmくらいだったという。Photo by Dive Family Yellow 川坂秀和さん

少しワイドに撮ったバージョンのサクラダイ。こちらも機材の装備は同じ。Photo by Dive Family Yellow 川坂秀和さん
透明度が低い中で撮影するからこそ、ライティング技法や被写体へのアプローチも学べるし、生えモノを代表とした動かない生き物や手元の魚に目がいきやすいのだろう。
メリット4:レアものに遭遇できる

オキノスジエビ Photo by Dive Family Yellow 川坂秀和さん
この時期はレアものに出会えるチャンスがあるというから、春濁りだからといって潜らないのはもったいない。
川坂さん
春は深場からレアものが登場する季節でもあります。たとえば、産卵のために例年4〜6月あたりに深海から上がってくるオキノスジエビ。今年は伊東では4月10日に発見されたのを皮切りに、和歌山県の須江でもすでに観測されています。伊東、IOP、大瀬崎、伊豆大島あたりでも今年はチャンスがありそうな予感がしてます。今回のように4月頭での産卵の観測例は過去にもあまりなく、通常であれば6月に見られることが多いので、この春はまだまだ産卵のタイミングが訪れることが期待できます。
もはや透明度がさがるからと尻込みする理由はなくなってきたように思える。
メリット5:春濁りによる春の息吹を感じられる

Photo by Dive Family Yellow 川坂秀和さん
上記写真からもわかるように、伊東といったら美しいソフトコーラルが名物といっても過言ではないが、このソフトコーラルも春濁りなくしては育まれないという。
川坂さん
春濁りの余韻を引きずる5月くらいになると、雨が降る日が多くなっていきます。雨が長引くと、伊東市の内陸に作られた奥野ダムから水が放流し、川から海へ流れて、春濁りの海をかき混ぜるんです。東伊豆を南から北に流れる黒潮の影響も相まって、海中の栄養分がより循環します。これがソフトコーラルを育てる下支えとなっていると考えられています。ソフトコーラルたちは、この栄養分で一気にポリプを咲かせるんです。
伊東に広がるソフトコーラルの壮大な景色は、春濁りをベースに、雨によるダムからの放水、黒潮の流れといった複数の要因が重なって、作り上げられたようだ。そして、栄養分をたっぷり吸収したソフトコーラルはたくさんの生物の活動の拠点となり、ここからたくさんの命が誕生し、そして育まれ、次の命へと繋がってゆく。
このことを踏まえると、春濁りというのは、海中世界の一年の始まりであり、春の息吹を感じられる重要なイベントなのだろう。春からダイビングをスタートさせるのも、とても趣があるのでは。まだ躊躇されているなら、だまされたと思って一度潜ってみるのもいいかもしれない。
最後に、伊東の現地情報を。2021年4月初旬には一旦春濁りの影響は出たものの、21日時点ではあまり見られず、透明度は10~15mに回復しているとのこと。といっても、この先どうなるかはわからないので、ダイビングプランを立てるときは、お世話になる現地ダイビングショップに海の状況を確認するのがよいだろう。

日本有数のダイビングエリア「伊豆半島」の東の玄関口「宇佐美」に店舗を構えるダイビングショップ。ホームグランドにしている「伊東」の海まで近く、天候が悪く潜れない場合は西伊豆へ移動するにあたってもとても便利な位置づけにあり、ホームグランド以外の海でもお客様のリクエストに可能な限りお答えしています。