ダイビング講習中の事故、和解事例「待機させていた講習生がいない!」
和解によって表に出てこない事故事例
裁判所に損害賠償請求事件が提起された場合でも、多くのケースが最終的には判決ではなく、和解で終わっているのではないかと思います。
例えば、東京地方裁判所における交通事故による損害賠償請求訴訟に関して言えば、7~8割程度は和解で解決でされています。
判決では、敗訴した方が高等裁判所に控訴することもあり、紛争解決が長引きます(高等裁判所まで争えば3年以上はかかると思います)。
しかし、裁判は当事者双方にとって精神的に負担になりますし、打ち合わせの時間などの経済的コストもかかりますので、できれば早めに解決したいということになります。
まして、ダイビング事故では、ダイビングショップとお客様、あるいはガイドダイバーとお客様という形で、知り合い同士の紛争であることが多いため、円満解決である「和解で終わりにした」という話しがでやすくなります。
和解になってしまうと、判決とは異なりほとんど事故の内容などを知ることができなくなってしまいますが、事故防止の観点からはそれは望ましいことではないと思います。
和解条項の内容に触れることはできませんが、和解で終わっている事故についても、お話しできたらと思います。
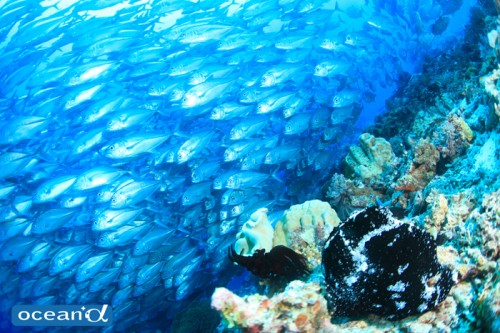
待機させていた受講生がいなくなった事故
講習中、インストラクターが受講生を海底で待機させていたところ、受講生がいなくなってしまった事故を扱ったことがあります。
インストラクターはベテランで、面倒見がよく受講生からもお店からも評判の良い方でした。
事故当時は6名の受講生の担当でしたが、潜降ロープで2名ずつ降ろし、海底まで着底させると海底に張られたロープを受講生に握らせて待機させ、自分は海面に浮上して2名の受講生を降ろすという作業を3回繰り返して、受講生6名を海底まで降ろしました。
海底に6名全員が降りたので、少し移動をしようと思い、受講生に中性浮力をとってもらったところ、1名の受講生がフワフワと浮き上がってしまいました。
インストラクターは他の5名の受講生には「やめ」と指示し、その場での待機を命じると、自分は浮き上がってしまった受講生の後を追いました。
海面近くで受講生をキャッチし、大丈夫か確認した後、浮き上がってしまった受講生と一緒に再び皆が待つ海底に戻ってきたのですが、潜降している途中で待機を命じた受講生らの様子を確認したところ、既にその時には1名足りなかったということです。
なお、受講生たちがフィンで海の底の砂を巻き上げてしまったこともあり、透明度はあまり良くない状況でしたが、インストラクターが浮き上がってしまった受講生を追いかけ、戻ってくる間は10秒もかかっていませんでした。
インストラクターは講習を中止し、直ちに付近を探し回りました。
その後、講習をした場所からかなり離れた浅瀬で意識を喪失している受講生を発見しました。
なお、海洋実習をした場所は受講生が流されてしまうようなところではない場所でした。
裁判における争点と裁判所の見解
裁判ではインストラクター側として、「ロストをしたのではなく、その場に待機をしていることを命じたのに、受講生の方から離れて行ってしまった事案である」ということを強調しました。
インストラクターは「待機」ということを命じており、受講生がその指示に従わなったと考えざるを得ない状況であったためです。
一方、相手方からは「経験のない受講生が自分の意思でグループから離れたとは思えない。他のグループと間違えるなどしたのかもしれない。受講生が間違えたときのフォローがされなかった」等の話がありました。
証人尋問までが行われました。
受講生側からの希望で、居なくなった受講生のバディに対しても証人尋問が行われましたが、受講生がその場を離れてしまった経緯はまったくわかりませんでした(初めてのダイビングで他人のことを見ている余裕はなかったようです)。
裁判官からは「中性浮力を失った受講生がいれば、インストラクターはその後を追わざるを得ないであろうし、インストラクターに過失があったということはできないと思う」という趣旨の話がありました。
ただし、受講生のうち誰かが中性浮力がとれなくなってインストラクターがその場を離れたとき、残された受講生全員は必ずインストラクターの指示通りの適切な行動をすることができると考えてしまっていいものかという話もありました。
その上で、受講生自らがその場を離れたと考えられることなどを考慮した和解案が裁判所から提示されました。
裁判を通しての感想
裁判官はダイビングを知らない方がほとんどですし、また、結果責任のように、「不幸な結果が生じたのだからダイビングショップが賠償金を支払えばいい」と安易に判断してしまう場合もあります。
しかし、本件についてはそのようなこともなく、「予測することができる事故だったのか」「事故を回避することは可能だったのであろうか」という過失の基本的構造に従って判断した上で、「インストラクターに過失があったと言うことはできないだろう」という話になったのだろうと思います。
ただし、受講生が必ずしも適切な行動をとれるとは限らないということは裁判所の指摘する通りで、思いもかけないようなことが起きてしまうことがあるのです。
インストラクターの方には、なお一層、想像力を働かせて受講生を指導していただくことをお願いする次第です。









