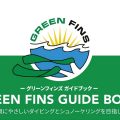Green Finsワークショップがインドネシアで開催、日本からも参加で持続可能な観光へ貢献
ダイビングやシュノーケリング業界の環境保全基準と認定制度として世界中で採用が進む「グリーン・フィンズ(Green Fins)」。インドネシア(※)では、このグリーン・フィンズの推進を強化し、海洋観光を持続可能な形に進化させようと、2025年2月18日〜19日にジャカルタでナショナルワークショップが開催された。インドネシア政府や国際団体、地域のダイビングショップ、そして日本、フィリピン、タイ、マレーシアそれぞれの支部の代表、その他関係者が集まり、実践的なロードマップの構築に取り組んだ。
※インドネシアは、世界有数の海洋生物多様性を誇る“コーラルトライアングル”の中心地であり、観光ダイビングの約7割が海洋保護区内で行われている。さらに、政府がブルーエコノミーを国家戦略として進めており、グリーン・フィンズの導入を後押しする体制が整いつつある。


グリーン・フィンズは、国連環境計画(UNEP) と The Reef-World Foundation が共同で推進する国際的な環境基準で、ダイビングやシュノーケリング業界における持続可能な観光を促進することを目的としている。この取り組みは、環境ガイドラインを提供し、海洋観光業者が環境への影響を最小限に抑えるための支援を行っている。
インドネシアで描かれた“青い未来”の設計図とは?
このワークショップは、The Reef-World Foundation、UNEP COBSEA(国連環境計画 東アジア海域調整機関)、Coral Triangle Center(CTC) の共催で、ジャカルタ市内のホテルにて開催された。支援には、IUCN(国際自然保護連合) の Blue Natural Capital Financing Facility(BNCFF)が入り、政策面・財政面の両軸からインドネシア国内でグリーン・フィンズの取り組みの強化に向けた議論が行われた。

The Reef-World Foundationのオペレーションディレクター、JJ・ハーヴィー氏が登壇。グリーン・フィンズの実践的な展開に向けた国際的な連携の重要性を強調した
ワークショップの中では、海洋保全と観光のバランスをどう保つか、既存政策への統合、実施コストと収益構造の課題などをテーマに、アジアの他国からの知見も交えた活発なセッションが続いた。

参加者たちによるグループワークの様子。国際的な視点から、グリーン・フィンズの強化に向けた実行計画を練り上げていく。
沖縄県恩納村での導入事例も各国に紹介
このワークショップでは、日本、フィリピン、マレーシア、タイからの参加者によるプレゼンテーションも実施され、日本からは沖縄県恩納村でのグリーン・フィンズ導入事例が紹介された。恩納村は日本初のグリーン・フィンズ導入地域で、2022年に最初のダイビングショップが認定を受け、恩納村役場や恩納村マリンレジャー協会が中心となり、持続可能な観光とサンゴ礁保全の両立を目指している。今回のワークショップでは、日本国内に広げるための課題や取り組み、資金調達の事例などが共有され、他国への応用にもつながる示唆を提供した。
海と向き合いながら楽しむためのダイバーの選択肢グリーン・フィンズ
グリーン・フィンズは、国や組織だけが取り組むものではない。ダイバー一人ひとりが環境に優しい選択を重ねるための指標となる。たとえば、生物に過度に接近しない、ごみを見つけたら拾うなど、海にやさしいダイビングをするための行動を示している。こうしたアクションやグリーン・フィンズ認定のダイビングショップを選ぶことは、環境保全の一歩であると同時に、未来のダイビング体験をより豊かなものにしてくれる。